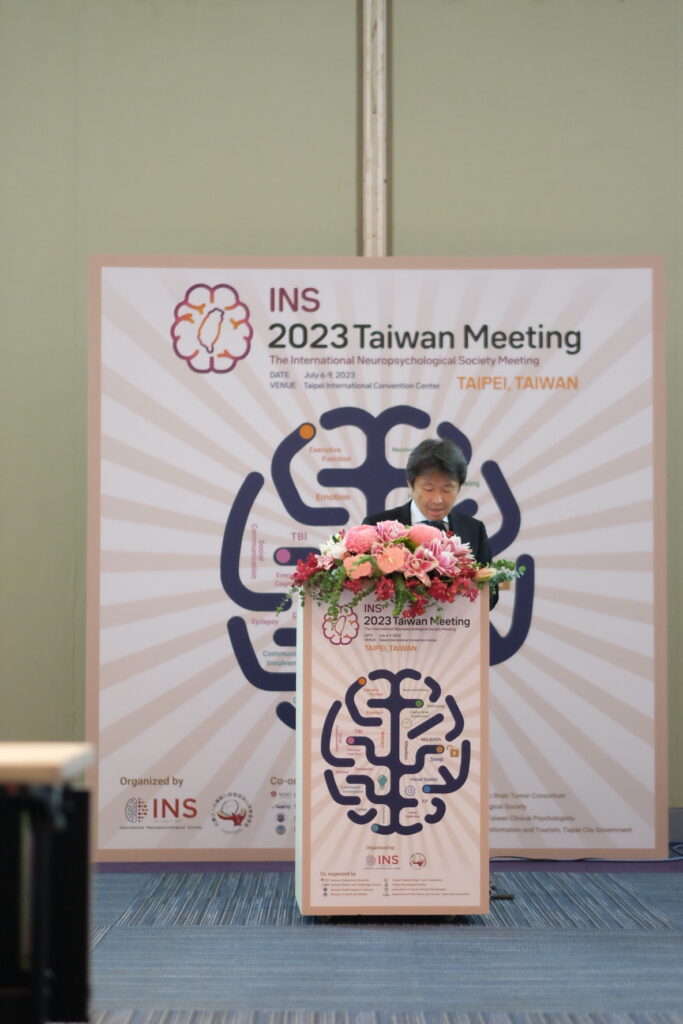ケアスル介護のHPに「介護において家族を支える大切さ」と題した文章を寄稿しました。
-
最近の投稿
お問い合わせ (Contact)
〒192-0393
東京都八王子市東中野742-1
中央大学文学部(3号館)3820号室TEL:042-674-3842(共同研究室)
FAX:042-674-3742(直通)
E-mail: green(*)tamacc.chuo-u.ac.jp
(*) を@に置き換えて下さい.Postal Address
742-1 Higashinakano Hachioji-shi, Tokyo 192-0393 JapanTel/Fax: +81 426 74 3742
E mail: green(at mark)tamacc.chuo-u.ac.jp